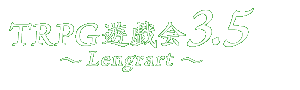ホーム > SandBox > ある男の話
#contents
*ルアーブルの港に降り立って [#d95e8e0a]
照り付けてくる乾いた日差しの下、私は石畳の上に一歩を踏み出した。
「――その荷物は向こう、あそこだよ! ほら、後がつかえてる! さっさと行きな!」
赤毛の女船長の声に急かされて、私はふらつく足でせっせと麻袋を運ぶ。
中身はクオ麦だろうか。漂う潮の匂いが私の鼻腔を刺激する。 ――すぐそこの海からの匂いかもしれないが。
それにしても、人が多い。こうして船から降りて少し見回すだけでも、百人は見えるだろうか。
貿易港…… なのだろうか、ここは。中規模の船がいくつも停泊し、筋骨隆々の船夫たちがせっせと積荷を降ろしている。私のように筋骨隆々でないものもいるが、手際は良い。
「そら兄ちゃん、きょろきょろしてっと転んじまうぞ!」
「あ、ああ。済まない」
そうしていると、後ろから陽気な笑い声を伴う声。
見れば、同じ船内で何度か顔を見た、熟練の船員だった。
「ここは貿易港なのか?」
「そういう区別じゃねえな。ここは中型船――ほら、喫水があるだろ? 船の底から水面までの距離だ。あれと船のガタイで区別してんのさ」
「――ああ、なるほど」
何故、とは言わずにその船員は私の疑問にすらすらと答えてくれた。
「ここはドルフィンポートつって、向こう側にはもっと小さいのが泊まるシャークポート、向こうには大型船が泊まるホエールポートがある。その向こうは軍港だな」
「そういう区別か」
船員が指したその方向を見つつ――街並みと小高い丘に阻まれて見えはしなかったが――私はようやく背中の麻袋を、同じような麻袋の山の隣へと置いた。
「お疲れだったね。さ、ここがルアーブルさ。夢を掴んでおいで」
女船長にそう言われて背中を押され、私は晴れて一時船員から自由の身となった。
先程は麻袋を運んでいた私だが、何も船員というわけではない。あの女船長の貿易船に載せてもらう代わりに、一時の船員として働いていただけだ。
個人的には旅船で優雅に来たかったが、そうもいかなかった。私はラクナウの方から乗ってきたわけだが、向こうの海運ギルドでルアーブル行きの旅船の部屋の値段相場を聞いたら、2000rkからだと言われたからだ。海賊どもの縄張りの近くを通る航路か、遠洋を通る遠回りの航路か。どちらにしても危険で金がかかるとのことだった。
払えないわけではなかったが、路銀の半分以上が飛ぶ。安いのか高いのか分からなかったので躊躇われるというのもあった。そこでその場で相談してみたところ、あの女船長が船員を募集しているとのことだったので、頼み込んで片道船員として雇ってもらったのだ。
ちなみに二隻からなる小さな海賊が沿岸での道中一度だけ襲ってきたが、私があわあわしている間に、女船長が直々に三連バリスタを打ち込んで撃退していた。
一応、給金も受け取っている。キリよく1000rk。高いのか安いのかは、やはり分からない。それなりの大金であることは確かだが。しかし、もし2000rk払っていた場合との差を考えると、3000rkの得をしたことになる。そう考えると凄いのかもしれない。
「――ようし、そら兄ちゃん、飲みに行こうぜ!」
ばんっと力強く背中を叩く逞しい掌。見れば、やはりあの船員だった。他の船員たちもいる。
「仕事の後は飲んで寝て、クオ=ルート様のケツを拝む夢を見ながら明日に備える! お決まりだ! さあ行こうぜ!」
「その表現は多少いかがなものかと思うが。しかし、いいのか?」
「こまけえことは気にすんな! アグ=ヴァ様にケツの穴が小せえって怒られちまうぞ!」
がっはっはと豪快に笑う船員。
あまり断れる雰囲気でもないので、私は多少引け目を感じつつも、彼らの好意に甘えることにした。
「分かった。君たちとの出会いをクオ=ルート神を基としたナインズに感謝を」
「そうこなくっちゃな!」
船員たちは道々、見目のいい女たちや、港沿いの小バザーの露天に視線を向けつつ、最寄りの酒場へ。
看板を見る。 ――ふらつく海猫亭。どうやら船夫たち御用達の店であるらしく、店内は昼を過ぎてしばらくだというのに、喧騒で満ち満ちていた。
「よく冷えたドランカラムをくれ! レモンの輪切りも頼む!」
「待ってな!」
注文の声に威勢良く答えるのは、見目の良い娘。小さめの体型の割に、発達した上腕筋はドワーフだろうか。ドワーフは海の傍では仕事をしないと聞いたものだが、迷信は迷信ということらしい。
「無事に港の土を踏めたことに乾杯!」
熟練の船員の音頭で、私たちは乾杯を交わし、飲んで食べて、そして歌った。
とにもかくにも、私はこうしてルアーブルにたどり着いたのである。
*最初の夜の帳 [#m717bf65]
ゆっくりと、雑多な港沿いの街並みが夕に沈む。
内地にある、大魔法学院を擁する都市では、まだ未熟な生徒が都市の街灯に“ライト”を付けて回るという。
ルアーブルは大都市ではあるが、流石にそこまでではないようだった。
「宿は…… 向こうの通りか?」
誰にともなく呟きながら、酒場で聞いた道を不確かながら私は行く。
船員たちとの宴が長引いてしまったのは、少々不覚だった。本当ならばこんな時間になる前に、部屋は取っておかねばならないのだが。
ランタンを翳しながら歩くというのは馬鹿にならない出費だし、そもそも官憲の手を煩わせることにもなりかねない。
そう思って私の足は酔いで多少ふらつきながらも急ぎに急いだのだが、やはり遅かったようだ。尋ねた七軒の宿はいずれも満室で、私が滑り込む余地は何処にもなかった。
この分では、他の宿も満室だろう。
「――どうしたものか」
通りの端、静かに流れる運河のほとりで、私はしばし途方に暮れた。
流石にこの大都市の中であっても、土地勘のない場所で、いい加減に野宿をする勇気は私にはなかった。
この地は夜の帳が落ちかかっても十分に暖かく、体調を崩しはしないだろう。
だが、それよりも、何処であれ一番恐れるべきものは人間であることを、私はよく知っている。
「別の通りになら、まだ希望はある、か?」
視線の向こう、運河を越えた向こうにも、人々の営みの灯りはまだ見えている。
だが、夕に照らされる建物や、薄暗闇が差し込みつつある通りに視線を滑らせれば分かる。この向こうはいわゆる貧民層に近いのだと。
流石にこのルアーブルでは新参もいいところの私が、ここより向こうに踏み込む勇気も、また存在しなかった。
「……どうしたものか」
「――どうしたの、オジさん」
不意にそんな声が聞こえてきたのは、背後からだった。
私はゆっくり振り向いた。腰のレイピアについ手が掛かってしまったのは、あまり良くない癖だ。生きるためには有効ではあるが。
視界に入ってきたのは、褐色の肌の娘だった。
「宿が、取れなくてね。途方に暮れていた、ところだよ」
わざとゆっくり話し、その間に相手の様子をさりげなく観察する。
くすんだ銀の短髪、黒目、褐色肌。見目は悪くはない、むしろ良い方だが、発育は良い方ではない。僅かに覗く耳は少しだけ尖っており、恐らくハーフエルフであることを伺わせた。
身に付けているものは、薄汚れた短衣に、革の胸当て、腰当て、ブーツ。腰当てのベルトに差している短剣とポーチを見る限り、スカウトかレンジャー、あるいはシーフだろうと予測ができる。
(書きかけ)